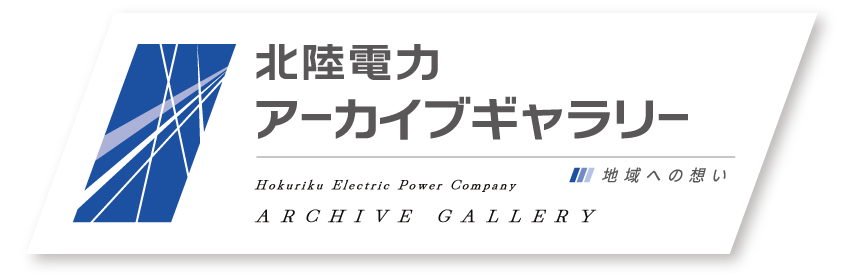- アーカイブギャラリー
- 4 発展する北陸 多様な電源開発
4 発展する北陸 多様な電源開発
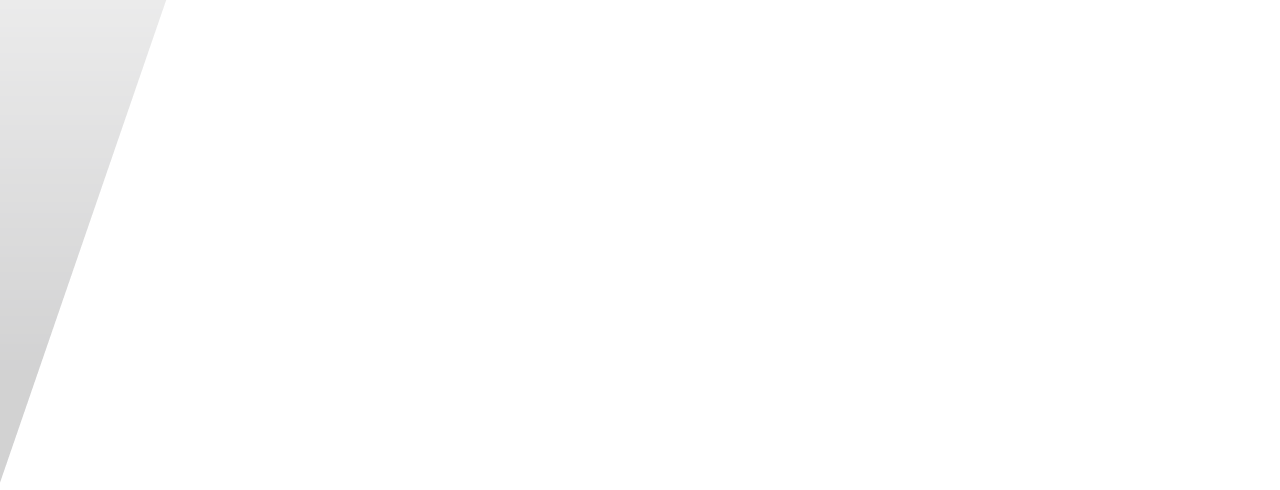
需要増大に合わせた火力発電の推進
高度経済成長による電力需要の伸びに対応するため,北陸電力は1964年(昭和39),富山火力発電所を建設。その後も福井火力発電所など,石油火力発電所を次々建設しました。1973年(昭和48)からの二度にわたるオイルショック(石油危機)は,石油の価格高騰と供給不安を招きました。電力の安定供給を守るため,石油から石炭への燃料転換を図るとともに,将来のエネルギー源として原子力発電の導入に着手するなど,電源の多様化を推し進めました。また,開発された電源の一部は,関西電力・中部電力などに融通して広域運営されています。
1984年(昭和59)には,富山新港共同火力発電所の燃料を石油から石炭に転換し,海外炭火力の開発に取り組みました。

(2001年に2号機,2004年に1・3号機を廃止済み)
オイルショックを踏まえ
燃料を多様化
平成に入り,石炭専焼の敦賀火力発電所[1991年(平成3)に1号機,2000年(平成12)に2号機],七尾大田火力発電所[1995年(平成7)に1号機, 1998年(平成10)に2号機]の運転を次々に開始しました。
両発電所とも,主蒸気・再熱蒸気温度を上昇させ熱効率を向上するとともに,最新の環境保全対策設備を導入しています。その一方で,老朽化した石油火力を順次廃止,設備運用の効率化を図っています。
その後も,地球温暖化による気候変動対策としてCO2排出量を大きく抑えるLNG(液化天然ガス)を燃料とするコンバインドサイクル発電にも取り組み,2018年(平成30)11月富山新港火力発電所LNG1号機が営業運転を開始しました。さらに,2033年の運転開始をめざして富山新港火力発電所構内にLNG2号機の建設も計画しています。

ベストミックスを目指し準国産
エネルギーの志賀原子力発電所建設
原子力発電は,供給安定性,経済性に優れているだけでなく,発電時にCO2を排出せず,地球温暖化対策,カーボンニュートラル達成に向け有効な発電方法です。
北陸電力は,電源のベストミックスを達成すべく1957年(昭和32)に準国産エネルギーである原子力発電の導入検討を開始しました。1967年(昭和42)には建設地点を石川県志賀町とする「能登原子力開発計画」を策定し,その後も地域の方々と粘り強く話し合いを続けながら,用地取得,漁業補償,国の審査,建設工事等を進めました。
計画策定から26年後の1993年(平成5)7月に志賀原子力発電所1号機(54万kW),その後,2006年(平成18)3月に2号機(135.8万kW)の営業運転を開始しました。
志賀1・2号機がベースロード電源の中心となることによって,石油・石炭などの化石燃料価格の変動を受けにくい,エネルギーセキュリティを確保した電源構成を実現しました。
2014年(平成26)には,2011年(平成23)の福島第一原子力発電所事故を踏まえた,志賀原子力発電所2号機の様々な安全向上施策が国の新規制基準に適合していることを示す申請書を原子力原子力規制委員会に提出しました。現在も原子力規制委員会による審査は続いており,最新の知見を適切に反映させながら着実に審査を進めています。

電力の品質を追求した
送変電設備の拡充
北陸電力の発足当初,送電線の最高使用電圧は77kVでしたが,急増する電力需要に伴う電源開発に対応するため,設備を拡充してきました。
1953年(昭和28),富山県の神通川水系の発電所開発に伴い,初の154kV送電線となる伏木線,富山線,見座線を新設し,以降は154kV送電線を基幹送電線として管内全域に張り巡らせて供給信頼度の向上を図りました。
1964年(昭和39)には初の超高圧送電線275kV新富山幹線を新設。その後も,中央幹線や加賀嶺南線の新設を進めるなど,火力発電の導入に伴う系統規模の拡大・強化に取り組みました。
1981年(昭和56)6月には,能登地区への安定供給を図るために500kV設計(275kV運用)の能登幹線を新設し,これによって北陸電力の系統は,加賀変電所を中心とする275kV系で一元運用することとなりました。
平成に入ると,電力需要と電力系統の拡大に対応して電力需給の安定化を図るため,中部電力との500kV連系によって相互応援能力を高めるとともに275kV系統を500kVに昇圧することによって広域運営を一層推進することとしました。